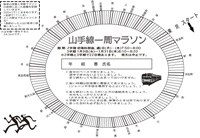6年家庭科調理実習
2009年01月29日
![]()
6年生が、1月26日に、家庭科調理実習を行いました。取り組んだのは、「お弁当のおかず作り」です。野菜(さやいんげん、にんじん)のベーコン巻き、ちくわのきゅうり詰め、三色(きゅうり、チーズ、ミニトマト)スティックの3品を作りました。
3学期の家庭科では、学習テーマのひとつとして「食事を通しての家族や友達との語らい」を設定しています。今回は、お弁当のもつ意味合いに着目しました。
家族や友達といろいろな所に出かけたとき、いっしょにお弁当をいただくと、会話も弾み、楽しいひとときを過ごすことができます。手作りのものであれば、込められた愛情や思いも伝わってきて、彩りや料理の味もさることながら、いっそう味わい深いものになります。
中学生になると、学校にお弁当を持っていく機会が増えることでしょう。自分でお弁当が作れるようになることで、より豊かな新生活を送ることができると考えています。
当日の実習は、次のように行いました。
【野菜のベーコン巻き】
さやいんげんは筋を取り、にんじんは皮をむいた後、5mmくらいのたんざく切りにして、軽くゆでます。

ゆであがったら、ベーコンで巻いて油で炒め、塩・こしょうで軽く味をつけます。


【ちくわのきゅうり詰め】
きゅうり1/2本を四つ割りにして、ちくわの穴に詰め、一口大に切ります。

【三色スティック】
一口大に切ったきゅうり、チーズ、ミニトマトをつまようじにさせば、できあがりです。

手間をかけただけ味わい深い「野菜のベーコン巻き」。手間もかからず簡単に作れて、しかもおいしい「ちくわのきゅうり詰め」と「三色スティック」。手作りの味わいだけでなく、彩りの鮮やかさから、目でも楽しめることを学びました。
また、友達といっしょに作ることの楽しさや喜びも味わうことができ、みな満足そうな顔をしていました。
![]()